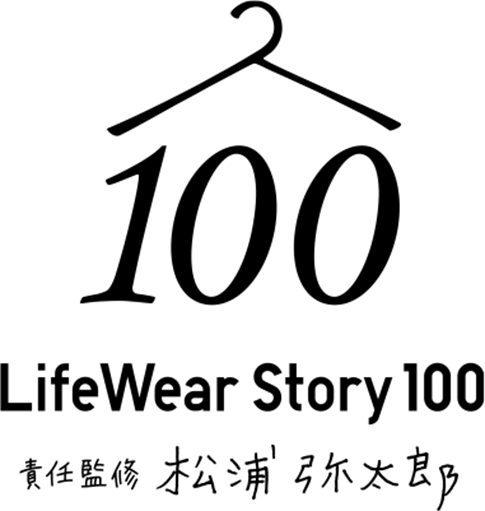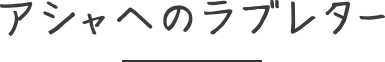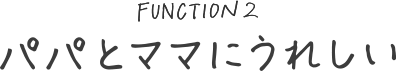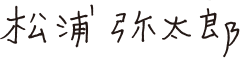「ちょっと待って!」というアシャの大きな声が後ろから聞こえた。
足を止め、後ろを振り返ると、手紙を持ったアシャが僕に向かって走ってきた。
「こんなラブレターもらったのはじめてよ。変なラブレターね。でも、あなたの気持ちが嬉しいわ。ありがとう! 明日、わたし休みなの。よかったらセントラルパークでサイクリングしない?」
こんな展開になるとは思ってもいなかった僕は驚いた。
「明日の朝、起きたら電話するから、あなたの電話番号教えて」
アシャは息を弾ませながら言った。
「うん、うれしいけど、自転車持ってないんだ」と答えると、「私もよ。レンタルできるから大丈夫。ね、行こ」とアシャは微笑んだ。
電話番号をメモに書いて渡すと、「じゃあ、明日ね」と言って、アシャはカフェに走って戻っていった。途中で後ろを振り返り、僕に向けて大きく手を振った。
次の日、朝7時過ぎにアシャから電話があった。僕らは10時にコロンバスサークルで待ち合わせして、レンタル自転車を借りにいくことにした。
「おはよう。いい天気でよかったね」
アシャはグリーンのTシャツにカットオフしたデニムのパンツをはいて、デイパックを背負って待ち合わせ場所にやってきた。
白のオックスフォードシャツ、カーキのショートパンツにテニスシューズをはいた僕を見て、「ショートパンツ似合うわね。はじめて見たわ」と笑った。

「時々、こんなふうにセントラルパークを自転車で走るの。一人で」
僕とアシャは、セントラルパークの自転車レーンをのんびり走りながらおしゃべりをした。
「ニューヨークでいちばん好きな場所どこ?」と聞くので、「ここ。セントラルパーク」と答えると、「私も!」とアシャは言った。
「ニューヨークに来たばかりの頃、毎日セントラルパークで本を読んでいたんだ」と言うと、「私はいつも公園内を歩き回っていたわ。探検家のように。私たち似てるね」と言って笑った。
「街中はとにかく人が多いし、うるさいし、せわしくて苦手。ここに来ると気持ちが落ち着くの」
アシャはペダルをこぎながら、遠くの景色を見ていた。
「ねえ、子どもの頃、どんな子どもだった?」
「知りたいことを何でも知りたがる子どもだったよ。大人に質問ばかりして困らせるような。あとは一年中ショートパンツをはいていたよ。今思うと、どんなに寒くなってもショートパンツをはき続けることで、自分は強いんだ、と主張していたんだね。クラスにもうひとり、いつもショートパンツの子がいて、彼と競争していたんだ」
「何を競争していたの?」
「いつまでショートパンツをはき続けられえるのかの競争だよ。いわゆる我慢比べ。結局、冬になって雪が降ってもショートパンツをはいて学校に行った僕が勝ったんだけど」
「雪の日にショートパンツ?」
「そう、上はダウンジャケットを着ているんだけど、下は素肌丸出しのショートパンツ。みんなにすごーいと言われてご満悦だった」
「アハハハ、おかしい! でも、そういう子、私、嫌いじゃないわよ。そっか、だから、ショートパンツが似合うのね」
「じゃあ、今日は私と競争しよ!」
アシャは自転車のスピードを上げて走った。
「私は子どもの頃、自転車が大好きだった。はじめて自転車に乗った時、これでどこへでも行けると思ったの。毎日自転車に乗っていたわ。だから自転車が得意!」
僕も負けじとスピード上げたが、アシャには追いつけなかった。
「今日わかったのは、私もあなたも負けず嫌いってこと」
自転車を止め、大きな池のほとりのベンチで休んでいた時、アシャはこう言って、クスクスと笑った。そして、「ミスターショートパンツさん、よろしく」と言い、自分の手を僕に差し出した。
僕は彼女の手をはじめて握った。