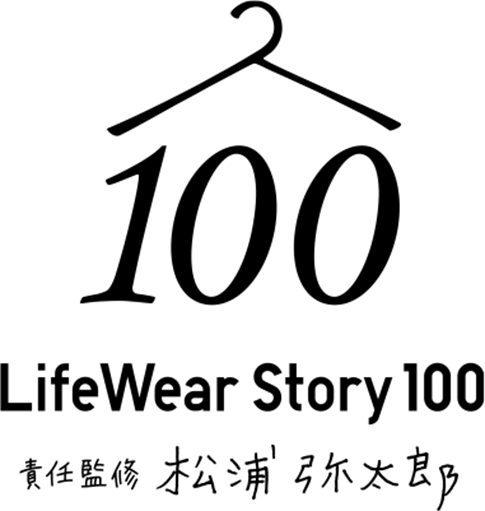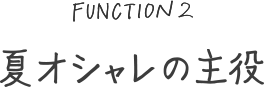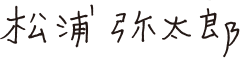「私はまるで『ミッドナイトカウボーイ』のジョーだった」とアシャは言った。
初夏のある日、僕らはセントラルパークのコンサバトリーガーデンの階段に座り、一人分のローストナッツとアイスティーを二人で分け合いながら、これまでの互いの人生を語り合った。
高校生の時、エチオピアから一人でニューヨークにやってきたアシャ。英語が話せなかった苦労、家族も友だちもいない日々、高校を卒業し、好きだったファッションの道へ進むが、イタリア人の母とエチオピア人の父の間に生まれたハーフであるがゆえ、健康的な肌色とスタイルの良さが仇になり、男性からのセクハラに悩まされた。
「今度こそ本当の恋愛ができる、と思って、人を好きになるんだけど、長く続いたためしがなかったわ。わたしが思い通りにならないとわかるとみんな去っていったわ。いつも嘘をつかれて騙されちゃうの。友だちは、何も考えずにエンジョイすればいい、というけれど、そうはなれなかった。私には夢がある。今しか出来ないことを精一杯やりたいの。ドレスメーカーになりたいの。そのためのデザインを学びたい。ただそれだけ。毎日いちゃついて、週末は夜通し遊びまわることが楽しいと思えないの。週に一度しか会えなくても、その一度をたっぷり楽しむ。そのほうがわたしはいい。わたしは彼氏のアクセサリーじゃないもの。いろいろな男性に出会ったけれど、うまくいかなくて人間不信に陥ったわ。遊べないのよ、わたし」
アシャはナッツをひと粒、空に向かって放り投げ、それを上手に口でキャッチした。
「一人ぼっちでいると、こんな遊びが上手になるのよね。ほら、ふたつ投げても落とさずに食べれるわよ」アシャは続けざまにナッツを投げて、口で受け止めるのを僕に見せて、無邪気に笑った。そして、四つまで出来ると自慢した。
「『コーヒーショップ』でバイトしたのは、わたしのように外国からやってきている人が多いからよ。みんな苦労している。あなたもそうね。仲間ができるから。わたしは一日に百杯以上、今、流行りのカプチーノを淹れて、ここに集まる『寂しきニューヨークの旅人』を励ましたい。負けるな!とね」

アシャは薄手のワンピースドレスを素肌に着て、裸足でスニーカーをはいていた。
「今日の服、すてきだね」と言うと、「ありがとう!これはわたしがデザインしたドレスなの。動きやすくて、楽で、それでいてフェミニンで健康的でしょ。この手のワンピースってセクシーになりがちだけど、そうならないように試行錯誤したの。バイトではいつもパンツルックだけど、今日みたいにデートの時はワンピースのほうが、女性は気分も上がるのよ。あ、でもスニーカーじゃ男はがっかりかもね。でも見て」と言って、アシャはスニーカーを脱いで、裸足になって立ち上がり、腰に手を当てて僕の目の前に立った。
「ね、どう? わたしのワンピースって裸足がいちばん似合わない?」そう言って、ワンピースをひるがえしながら、くるくると回って見せた。
「このあとどうする? どこ行く? 今日は裸足で街を歩こうかしら」
そう言ってアシャは、片手に脱いだスニーカーを持ち、もう片方の手で僕の手を引いて歩き出した。
五年前、僕らはそうやって休日を楽しんだ。
きらめく陽射しに眩しそうに目を細めるアシャの顔は美しかった。