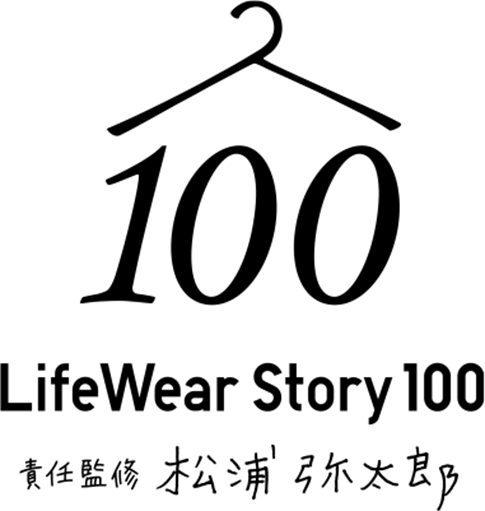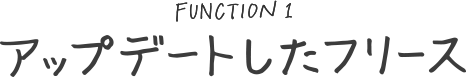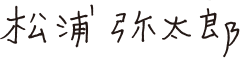物語を写真に撮る……。確かに僕は街を歩きながら、それはなんてことのない光景だけれど、見ていると、あたかも本一冊分くらいの物語が想像できるような、“ある状況”に足を止め、それを自分なりの言葉や文章で書き留めていた。
「写真か……」トーコさんと別れたあと、僕は道を歩きながら、もしカメラを持っていたら、僕は何を撮るのだろうと考えてみた。
その時、借りている部屋のクローゼットにカメラがあったことを思い出した。
部屋の持ち主のケイトは、ここにあるものはすべて自由に使っていいと言っていた。僕は急いで部屋に戻り、クローゼットを開けて、カメラを取り出した。
カメラはフリースのジャケットに包まれて置かれていた。おそらくフリースのジャケットをクッション代わりにしたのだろう。包みを広げると、ドイツ製の古いマニュアル式の小さなカメラだった。
しかも、カメラを包んでいたフリースのジャケットのポケットには、フィルムが2本入っていた。「このカメラ、使ってもいいのだろうか……」
これからケイトはピアノ教室のために、この部屋にやってくる。僕はその時にカメラを使ってもいいかと聞いてみようと思った。
その日の夕方、部屋にやってきたケイトに「カメラを見つけたけど、使ってもいいかな……」と聞くと、「あ、それは父のお下がりのカメラよ。ジャックに貸したけれど、結局使ってなかったみたい。だから、いいわよ使っても。そのフリースはジャックのものだけど、もちろんそれも着てもいいわよ」と、ケイトは、カメラなんか興味ないわ、と言うように答えた。ジャックとは、ケイトのボーイフレンドだ。
正直に言うと、僕にとっては、フリースのほうが嬉しかった。ニューヨークの秋がこんなに寒いとは思わなかったのだ。しかも、それまで僕は、フリースという素材の服を着たことがなかった。
フリースに袖を通し、ジッパーで前をしめると、軽くてあたたかくて、肌ざわりが良くて、そのまま横になって眠りたくなるような気分になった。
僕はフリースのジャケットを着て、肩からカメラを下げて街に出た。不思議なことに、フリースを着ていると、部屋から外に出た時のほうがあったかく感じた。

最初の一枚は何を撮ろうかと考えた。いや、何を撮らないといけないのか、撮るべきなのかと考えた。
僕は直感的に、今ニューヨークにいる自分を撮ってみようと思った。
僕は、道に面した家具屋の、ショーウインドウに置かれた鏡に映った自分に、カメラを向けた。
フリースを着て、カメラを構えた自分の姿がそこにはあった。僕はハッとした。その姿は痩せてみすぼらしかった。けれども、よく見ると、何かの物語の主人公のようにも思えた。
「旅とはいつも自分が主人公である……」いつかノートに僕はこんな言葉を書いていた。そうだ、主人公は自分なんだ。
僕は、フィルムをゆっくりと巻き上げ、絞りとシャッター速度を決めて、ピントを合わせ、シャッターを切った。