LifeWear Story 100とは。
ユニクロには、
流行に左右されず、
けれども、決して古びることのない、
長い間、作り続けている普通の服がある。
品揃えの中では、
とても地味で目立たない存在である。
コマーシャルにもあまり出てこない。
それらは、ユニクロが、
もっと快適に、もっと丈夫に、
もっと上質であることを、
長年、愛情を込めて追求したものだ。
それらは、ユニクロの人格と姿勢が、
目に見えるかたちになったものであり、
丹精に育てているものだ。
昨日よりも今日を、今日よりも明日と。
手にとり、着てみると、
あたかも友だちのように、
その服は、私たちに、
こう問いかけてくる。
豊かで、上質な暮らしとは、
どんな暮らしなのか?
どんなふうに今日を過ごすのか?
あなたにとってのしあわせとは何か?と。
そんな服が、今までこの世界に、
あっただろうかと驚く自分がいる。
ユニクロのプリンシプル(きほん)とは何か?
ユニクロは、なぜ服を、
LifeWearと呼んでいるのだろう?
LifeWearとは、どんな服なのだろう?
ここでは、LifeWearの、
根っこを見る、知る、伝える。
そして、LifeWearと、自分にまつわる、
ストーリーを書いていきたい。
LifeWear Story 100は、
LifeWearと僕の、旅の物語になるだろう。
松浦弥太郎
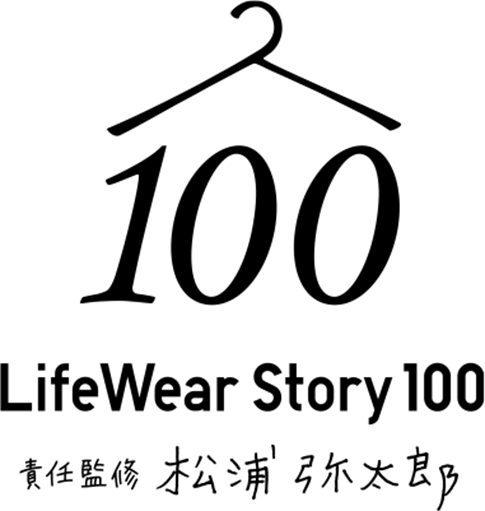


















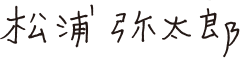

2015年頃、おそらくユニクロでは、その言葉はすでにあったと思うけれど、一消費者にとってその言葉は、当時まだ耳には入って来ていなかった。ユニクロにとってのLifeWearというひとつの思想というか、それはビジネスというよりも活動に近いものであると聞いた時、僕は強い衝撃を受けたんです。
だからといって、すぐに何かを始めるというイメージできるものはお互いに無かったんです。ただ、定期的にお会いして「暮らし」や「服」を語りあっていました。それと同時に、なぜか後輩編集者の亜童さんとも会っていましたね。